【福岡版】一般酒類小売業免許取得のポイント|プラウト行政書士事務所
2024年9月から酒類販売の規制が緩和されました。一般酒類小売業免許が取得しやすくなったため、食料品店でのお酒の販売や飲食店でのお酒の販売など、新たなビジネスチャンスが生まれます。
ここでは、一般酒類小売業免許の取得方法と必要書類について、酒類販売業許可に対応した福岡の行政書士が分かりやすく解説しています。
一般酒類小売業免許について

消費者、飲食店営業者等に対して酒類を販売できる酒類小売業免許は3種類あって、すべての種類の酒類を小売りできるのが「一般種類小売業免許」です。
この「一般種類小売業免許」は有店舗と無店舗といませんが、1つの都道府県内での小売りが条件です。また、小売業者間の売買は禁止されています。なお、「一般種類小売業免許」を1度取得すれば、免許の更新手続きはありません。
一般酒類小売業免許取得のポイント

一般酒類小売業免許の要件は大きく分けて4つあります。「人的要件」「場所的要件」「経営要件」「需給調整要件」です。この要件を申請書と添付書類で示すことが必要です。
人的要件
一般酒類小売業免許の申請者の国税・地方税が未納でないことが必要です。納税証明書を提出します。
また、酒類販売の知識や経験が問われます。酒類販売の経験が要件にみたない場合は、酒類販売管理研修を受講することで要件をみたします。

場所的要件
税区分を明確にすることが必要であるため、酒類販売の場所を他の製造所、販売店、飲食店と同じ場所に設けることはできません。
売り場に区割りがあり、決済の独立性を確立し、他の営業主体と区分けすることが必要です。
飲食店で一般酒類小売業免許を取得するときには特に大切になってきます。

経営基礎要件
経営基礎要件で大事になるのは「最終事業年度の決算で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと」「直近3事業年度の全てにおいて20%を超える欠損が生じていないこと」です。
法人は、3事業年度の財務諸表を税務署に提出します。個人は、3年分の確定申告書、源泉徴収票等を提出します。

需給調整要件
酒類販売は、仕入れ、保管、売上、在庫と他の販売と区分けすることが必要です。そのために受給調整要件があり、適切な販売管理が要求されます。

一般酒類小売業免許の申請書類及び添付書類
一般酒類小売業免許の申請書類と添付書類は、以下を参考にしてください。
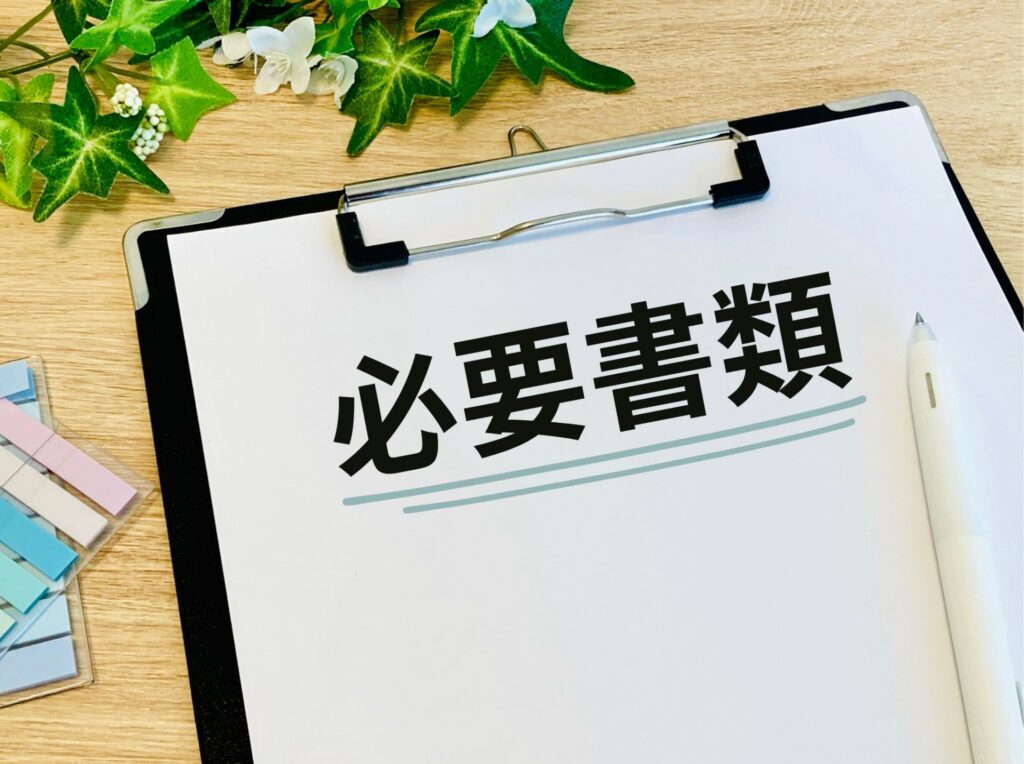
申請書類
- 販売場所在地及び名称
- 申請する販売業免許等の種類
- 販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法
- 販売業免許申請書次葉1(販売場の敷地の状況)
- 販売業免許申請書次葉2(建物等の配置図)
- 販売業免許申請書次葉3(事業の概要)
- 販売業免許申請書次葉4(収支の見込み)
- 販売業免許申請書次葉5(所有資金の額及び調達方法)
- 販売業免許申請書次葉6(酒類の販売管理の方法に関する取組計画書)
添付書類
- 酒類販売業免許の免許要約誓約書
- 申請者の履歴書
- 定款の写し
- 複数申請等一覧表
- 地方税の納税証明書
- 申請書次葉付属書類
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表・土地及び建物の登記事項証明書
- その他参考となるべき書類
- 免許申請書チェック表
福岡の酒類販売に対応したプラウト行政書士事務所
一般酒類小売業免許の申請には、申請書と添付書類を用意することが必要です。許認可になれない申請者は、手間と時間がかかってしまいます。
許認可専門の行政書士に依頼すると、税務署の審査で指摘されることは少なくなり、迅速に免許の取得が可能です。
本サイトの運営者のプラウト行政書士事務所は、酒類販売業免許に対応しています。福岡市近郊で一般酒類小売業免許取得を依頼者の費用を抑えて迅速に行っています。
福岡のプラウト行政書士事務所の酒類販売業免許のお問い合わせは以下からお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297)








