【福岡版】酒類販売業・製造免許における需給調整要件|プラウト行政書士事務所
酒類販売業・製造業免許申請は、需給調整要件を考えることが必要です。需給調整要件は、製造業や卸売業で特に問題になります。
ここでは、福岡の酒類免許対応の行政書士が「酒類販売業・製造免許における需給調整要件」についてわかりやすく解説しています。
酒類免許の需給調整要件
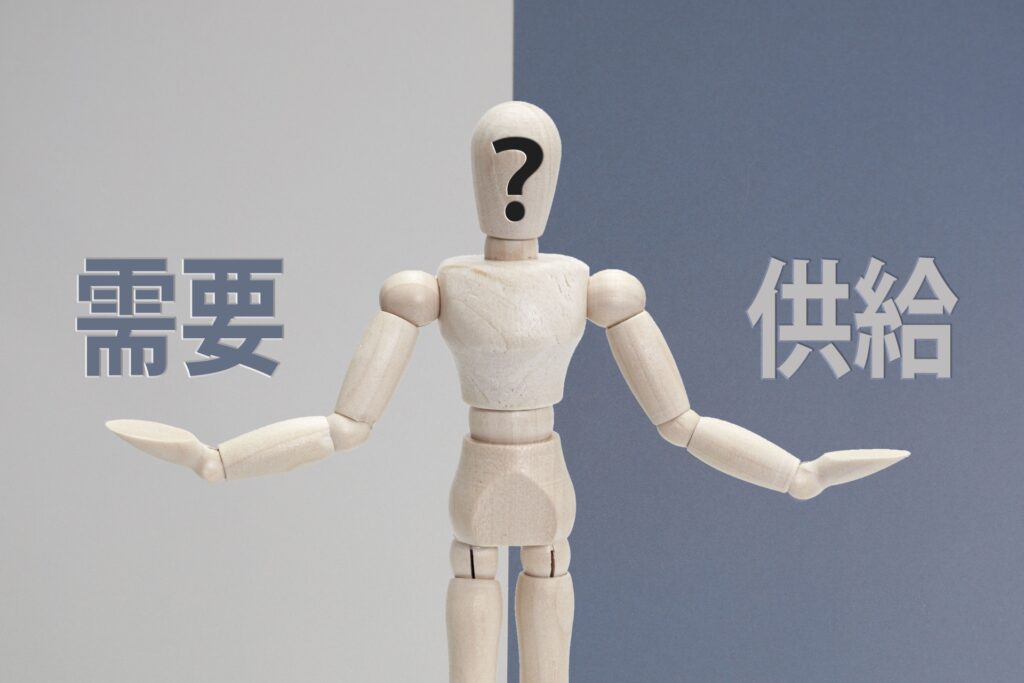
酒類販売業・製造免許の需給調整要件は「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合」に該当しないことです。
酒類免許を制限せずに製造業者や販売業者を増やせば、酒類事業者の過当競争等で酒類の需給の均衡が破られ、酒類免許制度の目的である酒税の保全に問題が生じることから、酒税の保全を担保することが需給調整要件の目的です。
需給調整要件の規制緩和

行政裁量で需給調整要件による参入規制は、既存業界の安定化につながるが、新規の参入者の排除につながるため、政府は需給調整要件の緩和が行われています。
酒類小売業免許
一般酒類小売業免許の需給調整要件は、段階的に緩和・撤廃され、現在は規制がほぼありません。
人口基準及び距離基準の廃止で、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、薬品、家庭電化製品、ホーム用品等の量販店等の新規参入が増加しています。
通信販売小売業免許
通信販売小売業免許の需給調整要件は、免許取得の要件で販売できる酒類を国産酒や高級輸入酒に限定しています。
また、地方の特産品等を原料とした酒類の一部が通信販売できるように法改正された。
酒類卸売業免許
酒類卸売業免許の免許可能件数による規制は残っています。
需給調整要件による免許可能件数が規定されている酒類卸売業免許については、平成24年9月の改正でも免許可能件数が増加する改正でないから、免許場数の増加はしていない。
酒類製造免許
酒類製造免許の需給調整要件はほぼ緩和されず、清酒など特定品目は新規参入が制限されています。
特産品焼酎(単式蒸留焼酎)や地場産米使用みりんの規制緩和、構造改革特別区域法による果実酒やその他の醸造酒、単式蒸留焼酎等を需給調整要件の不適用とする限定的に緩和されたが、限定された酒類の緩和でしかない。
近年の日本酒の輸出拡大に向けた取組みを後押しから、需給調整要件を適用しない輸出用清酒製造免許が設けられた。
酒類製造免許数はビールなどの需給調整要件が設けられていない免許については増加したが、需給調整要件で新規参入を規制されている清酒については免許数が減少しています。
しかし、参入規制から清酒製造業界では、廃業した酒類製造業者を買い取る新規参入は少なくない。
福岡の酒類販売業・製造業免許に対応したプラウト行政書士事務所
酒類販売業・製造業免許の申請には、申請書と添付書類を用意することが必要です。許認可になれない申請者は、手間と時間がかかってしまいます。
許認可専門の行政書士に依頼すると、税務署の審査で指摘されることは少なくなり、迅速に免許の取得が可能です。
本サイトの運営者のプラウト行政書士事務所は、酒類販売業・製造業免許に対応しています。福岡市近郊で酒類販売業・製造業免許取得を依頼者の費用を抑えて迅速に行っています。
福岡のプラウト行政書士事務所の酒類販売業・製造業免許のお問い合わせは以下からお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297)








